ユーザビリティ評価(使い勝手評価)
前述でデザインの主な判断基準を3つあげました。(A)アイデンティティ評価、(B)ユーザビリティ評価、(C)クオリティ評価です。
本項ではこのうちの(B)ユーザビリティ評価の判断規準の洗い出しについて説明しています。デザインを実際に評価する際はさらに判断規準をブレークダウンし、デザイン計画とのズレという形で判断していきます。その実際の事例については後述していきます。
ユーザビリティ評価とは使い勝手を評価することです。
製品の使い勝手は、想定のユーザ経験を満足させられるデザインになっているか、評価する規準をつくります。
ユーザビリティに限りませんが、評価する際に重要なことは何をどのように評価するかです。ユーザビリティの概念は該当する製品の広がりや性能向上・ユーザーインターフェース(以降UI)の進歩に応じて、今も議論がつづき専門家のあいだでは確定には至っていないようですが、ここではハードウエアを含めユーザー工学を提唱されている黒須正明氏の編著「ユーザビリティ・テスティング」より、ISO(国際標準化機構)により定められたISO9241-11をもとに、まずはユーザビリティという概念を考えていきます。
ユーザビリティとは以下の3項からなるとしています。
有効さ (effectiveness)
ユーザが指定された目標を達成する上での正確さと完全さを評価します。
効率 (efficiency)
ユーザが目標を達成する際に、正確かつ完全に実行するために費やしたリソースについて評価します。
満足度 (satisfaction)
製品使用に対しての肯定的な印象を与えられたか。および不快なことがなかったかを評価します。
これらの有効さ・効率・満足度はユーザビリティの性能を表す評価規準です。しかし本ログでは、デザインがユーザビリティに与えた結果を評価する規準が必要ですから、デザイン評価の段階では、製品をかたち作る諸要素全てが、ユーザビリティに対して最適解になっているかを評価したいところです。そのため評価の視点をUIを構成している目的となる概念別に変更し、以下の認知性、操作性、快適性という評価規準を用いたいと思います。
デザインによってユーザビリティを生み出す3つのポイント
認知性
製品を使う際に製品のアフォーダンスは適切か、またユーザと製品のインタラクションへ導くための合図となるUIのデザイン(以降シグニファイア)は的確に成されているか。
操作性
製品デザインがUIを適切にサポートしているか。一連の操作の流れ(以降シーケンス)を含みユーザへフィードバックは適切か評価します。
快適性
製品デザインはハードウエア、ソフトウエア共にユーザが製品を使った結果、製品を自身の認知下で完璧に制御できたか。また製品を使った際のUIやインタラクションにバグと感じる事象はなかったか、という評価も行います。
認知性・操作性・快適性の関係
ユーザビリティ(使い勝手評価)における快適性評価とは「製品の使い心地」を評価しますから、認知性と操作性が良いという評価だけでは前述した「有効さ」と「効率」の部分しか評価できません。
製品に対してユーザは、何ができるかという機能(以降ユーティリティ)と性能だけを求めているわけではありません。それはユーザビリティでも同じでその製品を使えるということだけではユーザは満足しません。製品が明確で認知性が良いシグニファイアを持ち、合理的な操作性を持つシーケンスと的確なフィードバックが与えられてだけでは快適性は完結しません。認知性と操作性だけが適切であれば満足する製品は、単に使えることだけを求める工場などにある産業用装置です。現在ではこれら装置も使い心地は大切に考えられるようになりましたが、製品の性格上ユーティリティ重視であることは変わることはないでしょう。
本ログでは一般ユーザが日常生活で使う製品を念頭に記していますから、使い心地を評価する場合、製品を自身の認知下でどの程度まで制御できたのか。またUIやインタラクションに認知を妨げるデザインやシーケンスにもバグと感じるコトはなかったか。これら快適性の評価が必要になります。
快適性は先に説明したアイデンティティ評価(特徴点評価)や、後で説明するクオリティ評価(作り込み評価)によって決まる因子の影響が大きく関係し相互作用を生みますから、これらの評価を含めて、本ログでは快適性という評価規準を用いたいと思います。
プロジェクトの段階に応じたユーザビリティ評価
ユーザビリティは実際にリアルなサイズのインターフェースと操作シーケンスを用いた評価でなければ、正確なテストは出来ません。デザイン開発を行っている段階でのユーザビリティ評価は、プロジェクトが既存製品のインターフェースを持ち越しで採用するのか、またはプロジェクトで新たなインターフェースを採用するのかで大きく変わってきます。
加えてデザインの開発段階のステップによってもユーザビリティ評価の目的は大きく変わってきます。
例えばアイデアを練っている段階では、主だったインターフェースをおおよその位置やサイズで配置して、ラピッドプロトタイプなどを作り、製品全体のフォルムの検討を行います。
次いで詳細にアプリケーションのデザインを詰める段階では、紙やPCアプリによるプロトタイピングモデルを作りシーケンスを検討しながら、インターフェースの配置や大きさをハードウエアにフィードバックしていきます。
そしてソフトウエアの実装を行いプログラムのミスを検出(以降デバッグ)を行う段階では、あらゆるユーザーの使い方(意地悪な使い方を含む)を想定し、シミュレータでテストを行った後、実製品と同等のインターフェースを実装した試作品で様々な実使用を想定した試験を行います。
このように開発段階で実施方法が異なるユーザビリティ評価ですが、このログではデザインディレクションについて記していますので、最も源流であるアイデアスケッチを評価する段階でのユーザビリティ評価について記します。
アイデアスケッチ段階でのユーザビリティ評価
まず製品をユーザが認知したとき、この製品は一体何が出来るのかをユーザーは探ります。先のアイデンティティ評価で用いた6概念(実体概念、機能概念、属性概念、価格概念、抽象概念、形態概念)により既存カテゴリーに即した製品であれば、ユーザーはすぐにその製品のユーティリティは分かるはずですが、既存カテゴリーに即していない外観の製品では何ができるかという可能性を、ユーザは製品の外観から想像して手がかりを捜します。
ユーザーが何をするものか?という「問い」に対し製品が示す可能性がアフォーダンスで、その結果としてデザインで用意したユーザに対する認知の手がかりがシグニファイアです。
ユーザーは初めて製品を見たとき製品全体の佇まいから一番目立つ部分に視線を経由させ、なにか触れても良さそうな部分となるシグニファイアを見つけます。この触れて良さそうな部分が、製品のインターフェースの入り口であれば、ユーザは迷わずに製品を使い始めることが出来ますから、ユーザビリティを良くしたいと考えている製品に対しては適切なシグニファイアになります。
どこを触って良いのか全くわからないものをユーザは不気味に感じ、触ってもらえない可能性があります。ですからユーザビリティ評価とは、まず触ってみようと思えるシグニファイアを有しているかを評価することから始まります。
そしてインターフェースに導かれたユーザーはインターフェースであらかじめ設定された操作手順に従い操作を行い、操作の結果を何らかのフィードバックを受けることでユーザビリティは完結します。これら一連のユーザーの行為を如何に考えてデザインしているかを、前述3つの視点(認知性・操作性・快適性)から使い勝手(ユーザビリティ)の評価を行う判断規準として取り上げます。
次項から、これらの一連の流れをユーザが認知しアクションを起こして行く順に考えます。
ではまた!

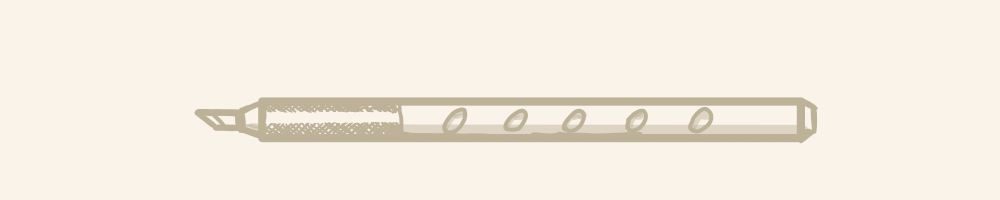


コメント